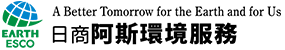衛生管理情報(3)「温度管理」の徹底で食中毒を予防(前篇)
發布日期:2020/8/10
新型コロナウイルスの影響で高まる食中毒のリスク
細菌性食中毒は、気温湿度が高くなり細菌が活発に増殖する5月から10月にかけて多発する傾向にあります。近年は、夏日・真夏日が記録的早さで観測される地域や、全国的に夏場の高温傾向が顕著な年も多くなっており、食品事業者にとって食中毒対策は、これまで以上に長期間にわたり、また地域を問わず強化すべき重要事項となっています。
また、本年は新型コロナウイルス感染症が人々の生活や行動に様々な変化を与えた影響で、食品事業者においても、業態や生産体制の変化など、例年とは異なる特殊な環境におかれているケースも多いと思われます。現在、新型コロナウイルス自体の食品を介した感染事例は確認されていませんが、事業体制の変化により、細菌性食中毒のリスクが高まる可能性が各方面から指摘されています。
具体的には以下のような例が考えられます。
上記のケースで起きる共通点は食中毒てあり、従って特に注意して取り組みたいポイントは;
中毒の予防には、食中毒菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」の3原則に基づいた様々な対策が必要ですが、次回は「温度管理」について取り上げ、その中でも特に疎かになりやすい「加熱工程のある食品」の温度管理について、注意すべき点をご紹介したいと思います。
食中毒予防に関連したサービスの例
出典:freepik
細菌性食中毒は、気温湿度が高くなり細菌が活発に増殖する5月から10月にかけて多発する傾向にあります。近年は、夏日・真夏日が記録的早さで観測される地域や、全国的に夏場の高温傾向が顕著な年も多くなっており、食品事業者にとって食中毒対策は、これまで以上に長期間にわたり、また地域を問わず強化すべき重要事項となっています。
また、本年は新型コロナウイルス感染症が人々の生活や行動に様々な変化を与えた影響で、食品事業者においても、業態や生産体制の変化など、例年とは異なる特殊な環境におかれているケースも多いと思われます。現在、新型コロナウイルス自体の食品を介した感染事例は確認されていませんが、事業体制の変化により、細菌性食中毒のリスクが高まる可能性が各方面から指摘されています。
具体的には以下のような例が考えられます。
| 飲食店のケース |
| テイクアウト、デリバリー(宅配)等の増加により、これまで調理した食品をすぐ提供していた事業者が、調理後時間をおいてから喫食する食品を提供するようになる。 ➔ 調理後喫食までの時間経過における温度管理等が不足することによる食中毒。 |
| 食品工場のケース |
| これまでと異なる生産体制(増産等)により、製造工程間における保管時の滞留が増加する。 ➔ 保管時に常温での放置などの温度管理不足や2次汚染による食中毒。 |
上記のケースで起きる共通点は食中毒てあり、従って特に注意して取り組みたいポイントは;
| 飲食店 |
| 飲食店のテイクアウトや宅配においては、「加熱後速やかに冷却する」「温かい食材を他の食材と一緒に盛り付ける時は、冷めてから行う」「温かいまま販売しない」「持ち運びの際には保冷材等を適切に使用する」、等の対応を行う。※調理後、できる限り2時間以内に食べてもらうよう、注意喚起も重要です。 |
| 食品⼯場 |
| 食品⼯場では、加熱後、冷却前の製品等について滞留時間の上限に関するルールを決め、作業者への周知徹底や確認を行う。 ※増産時などは、冷蔵庫等の保管スペースや冷却能力が維持できるかの確認も必要です。 |
中毒の予防には、食中毒菌を「付けない」「増やさない」「やっつける」の3原則に基づいた様々な対策が必要ですが、次回は「温度管理」について取り上げ、その中でも特に疎かになりやすい「加熱工程のある食品」の温度管理について、注意すべき点をご紹介したいと思います。
食中毒予防に関連したサービスの例
- 微⽣物管理上の各種課題に対する問題解決や改善活動のサポート
- 衛⽣教育(現場教育、講習会、専⾨教育)
- HACCP関連の各種認証取得、維持管理に関するサポート
- サニテーションマニュアル等の作成指導、現場定着指導
- 製造ラインや製造環境の洗浄消毒、清掃業務
- 各種設備改善⼯事

出典:freepik
(続く)
(ESCO News Letter 第9卷2號より抜粋)